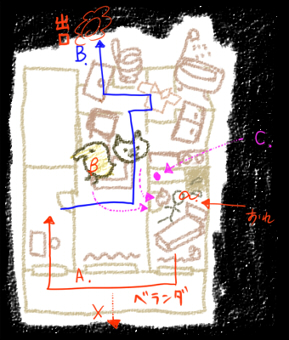「誰だっ!!」
不幸中の幸いと言うべきか。戸を閉める物音は、風の音と桐生の怒鳴り声にかき消された。
普段物静かな男だけに、怒った時の迫力が凄まじい。
服の隙間で息を殺しながら、口から飛び出そうになる心臓をなだめる。
飛び出たところで、元チーム・バチスタの二人にかかれば、あるべき場所に押し戻されるのが関の山だ。
「ん?」
「……風だよ。窓が開けっぱなしだったんだ」
拍子抜けしたバリトンを、やや高い声がなだめる。
わずかに光が漏れる扉の隙間から、俺は寝室の様子を伺った。
バスローブのシルエットが窓を閉め、カーテンの間から外を気にしている。
どうやら鳴海は、俺がバルコニーから逃げたと判断したらしい。
寝室の扉が閉まる音がして、桐生の大きな影が目の前を翳らせた。
俺は息をつめた。
が、桐生はクローゼットを気にすることもなく、狭い視界の端に消えた。
スプリングがきしむ音が聞こえ、シーツが乱れたままのベッドに腰掛けたらしい、ということがわかる。
続いて聞こえてくる、深いため息。
「……戸締りには気をつけなさいと言っただろう。
日本だって、今はそう安全じゃない」
「これから用事があるんだ。だから、帰って」
「そうか。なら、待っている」
「…………………」
「まだ、拗ねているのか」
「――義兄さん、僕は」
「リョウ、来なさい」
わずかに怒気をはらんだ声。
窓の影は動かない。
なんとか桐生に悟られずに、俺がここにいることを鳴海に伝えるすべはないものか。
数ミリの隙間から手を振ってみたものの、窓のほうを向き、こちらに背を向けた鳴海は当然気づかない。
「リョウ」
もう一度名を呼ばれ、鳴海がゆっくり振り返る。
クローゼットには注意を払わず、しきりに窓を気にしながら、
差し招かれるままに桐生の横に座ったようだ。
衣擦れの音。
不意に訪れる沈黙が生々しい。
つい先ほどまで、俺が鳴海と絡み合っていたベッドは乱れたままだし、
床には後始末のティッシュも転がっている。
そもそも玄関先には、俺の靴が出しっぱなしではなかったのか。
そのことを指摘しない桐生を不思議がっていたが、次の瞬間その疑問は解けた。
桐生の持病は確か、視野狭窄の発作を伴う狭隅角緑内障だ。
おそらく、今の桐生は文字通り、風呂上りの義弟しか目に入っていないのだ。
「――会いたかった」
桐生の声が、甘く囁く。
プライベートではこんな声も出すのかと、驚いている場合じゃない。
続いてバスローブの裾が割られ、鳴海の太腿がむき出しになる。
反射的に先ほどの鳴海の媚態が蘇り、俺は慌ててその情景を頭から追い出した。
現れるタイミングを完全に失った俺は、あまりに気まずい展開に、もはや出るに出られなくなっていた。
いくら桐生の視界が狭くとも、俺が出て行って気づかないはずがない。
しかも、しつこいようだが、今の俺は全裸なのだ。
「義兄さん」
ベッドの上に押し倒されながら、鳴海はまだ窓のほうを気にしていた。
目線をちらちらと外に向けながら、肩に埋まる桐生の顔をやんわりと押しとどめる。
「……ごめん。今はそんな気分になれないんだ」
鳴海の拒絶に、俺は静かに胸を撫で下ろした。
さすがにこの至近距離で、義兄弟に濃厚なラブシーンを繰り広げられるのは、精神的にキツすぎる。
途切れ途切れの光景に、俺はすでに充分打ちのめされていた。
「――そうか、すまない」
「義兄さんも長いフライトで疲れたんじゃない? 目に障るし、少し休んだほうがいいよ」
鳴海の優しい労わりに、俺は小さく頷く。
このまま桐生が誘導に乗り、熟睡してくれれば、あるいは脱出のチャンスもあるかもしれない。
「そうだな。汗も流さずにすまなかった」
「え?」
「シャワー、浴びてくる」
桐生が不意に立ち上がる。鳴海が慌てた様子でその腕を掴んだ。
「違うんだ。 そういう意味じゃなくて!」
鳴海は桐生をいなしながら、どうやら俺の逃走経路を冷静に推し量っていたようだ。
鳴海が立てた仮説は、おそらくこういうことだろう。
<鳴海が立てたであろう仮説>
バルコニーから脱出した俺(α)が、次に行うであろう行為は、二通りに分かれる。
A.そのまま書斎で息を潜めるか、
B.風呂場に服を取りに行き、脱出するか。
脱衣所には俺の服が脱ぎっぱなしで、風呂場に向かった桐生(β)がさすがに気づくリスクがある。
A→B移行ルートをとった場合には、下手すればリビングで鉢合わせしかねない。
よって、AもしくはBの確認が取れるまで、桐生(β)を寝室から出すわけにはいかない。
「それなら、お湯張ってくるから、ここで待ってて」
「シャワーでいい。汗を流せれば充分だ」
「汗なんか流さなくたっていいじゃないか」
「長いフライトの後だし」
「十時間なんて大した距離じゃないよ」
「いや、そんなことも、ないんじゃないか」
「義兄さんは十時間を超える手術だって、クリアーしたことがあるじゃないか」
「それとこれとは、また話が……」
「あの時義兄さんは言ったよね。
『患者を救おうとする熱意の前には、時間は意味を成さない』って」
「そんなこと言ったっけか?」
バスルームに向かおうとする桐生を、鳴海は必死で止める。
戸惑う桐生に、やがて鳴海はやっと整合性のある理由を見つけたようだ。
「たぶんそれは、ミヒャエル教授の言葉じゃないか?」
「……シャワーなら、後でいいじゃない」
打って変わって艶っぽい声で、鳴海は桐生の首筋をくすぐった。
「リョウ?」
「義兄さんの汗の匂い、嗅がせて……」
「さっきから一体なんなんだ? いくらなんでも落ち着きが無さすぎる」
「いいから、こっちに来て」
どう見ても情緒不安定で挙動不審な義弟に引っ張られるままに、桐生は再び倒れこむ。
ぎしり、とベッドが揺れた。
――これは俺を慮っての行動、だということはわかる。
さんざん俺とセックスした直後だ。さすがの鳴海も疲れているはずだ。……たぶん。
身を張って庇ってくれるのはありがたいが、鳴海仮説(正確には、鳴海が立てたであろう仮説)
には、致命的なピットホールがあった。
それは、俺(α)が、クローゼット(ここ)に隠れたというルートCの想定だ。
一見論理的に思える鳴海の計算には、小心者の羞恥心が想定されてない。
「義兄さん……」
「リョウ……」
「…………っ」
そして、結局こうなるのか。
俺に残された最後の手は、ここで行為が終わるのを待つことだけだ。
桐生と鳴海の名誉のために、何より折れそうな俺の心のためにも、目と耳はしっかり塞いでおこう。
落ち込むのは、下宿に帰ってからで充分だ。
「あ……リョ、リョウ」
狭い場所でうずくまり、汗だくになっている俺の耳に、低い喘ぎ声が飛びこんでくる。
俺はちらりと様子を伺った。
二人の足しか見えないが、鳴海を組み敷いているのは桐生のようだ。
「ちょ、そ、そんな、いきなり……く、あっ」
ところが、喘いでいるのは乗っかっている桐生のほうだ。
あの桐生が、こんななまめかしい声を出すとは。
思わず生唾を呑みこんでしまった俺は、おのれの喉が立てる音に冷や汗をかく。
一体、鳴海はどんなテクニックを使っているというんだ?
「ノ、ノォ、リョウ…!」
不自由な場所で一生懸命首を伸ばすが、糸のような隙間からでは、やはり絡み合う足しか見えない。
いやまてよ。あれは、鳴海の……手か……?
もう少しだけ視界が開けば、何をしているのかはっきりするはずだ。
そう考えた俺は、小さな隙間を広げようと試みた。
音を立てないように、少しずつ。
ほんのわずか開けた視界に、片目を寄せた俺は、何かにつまづいた
洋服の海に揉まれ見えてなかったのだが、足元には縛られた学術書の束が置かれていたようだ。
転びそうになった俺は、バランスを取ろうとして下げられたスーツを鷲掴む。
負荷に耐えられなかった掛け棒が外れ、木製のハンガーが次々と俺の頭に落ちてきた。
頭から布を被り、よろけた拍子に、クローゼットの扉が派手な音を立てて開いた。
遮るものもなく、俺はそのまま転がり出る。服が絡んで前が見えない。
「えっ……?」
「あ……」
何事かと驚くバリトン。そちらだったかと納得気味のビブラート。
布切れの間から、やっとのことで顔を出す俺の前に、Yシャツの前をはだけた桐生が立ちすくんでいた。
「そんな……まさか……」
細い目をさらに細め、呆然と俺の顔を見つめている。
「まさか……田口先生、まさか、あなたが……」
呟く桐生。俺はうつむく。時計が止まる。
他に言うべき言葉も見つからず、鳴海の高そうなスーツで下半身を隠しながら、
俺は立ち上がって頭を下げた。もちろん、全裸で。
「……お久しぶりです。桐生先生」
言葉を失う桐生の背後で、バスローブの前をかき寄せた鳴海が、気まずそうに身を起こした。